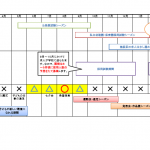「子どもたちって本当に可愛くて、保育士ってやりがいがあるな。でも…保護者対応が苦手・不安なんです」
と嘆く方…結構います。
- 子どもを保育するためには欠かせない
- 自信がなくても、苦手でも避けては通れない
「ま、いっか。保護者と話すの苦手でも」と開き直る方はいません。
保護者とうまく話せるようになりたいと思う方にはぜひ意識してほしいポイントをまとめました。
傾聴 話は遮らず最後まで聞く
- お母さんが話している時に話を遮った
- 話し出しが被ってしまった
そんな経験ありますよね。
タイミングを間違えてしまうことは誰にでもあること。ですが、意識してほしいのは保護者の話を最後まで聴きます。
保護者が話している途中で「でもね、お母さん(お父さん)…」と話し出すのはやめましょう。
話を聞く姿勢も大切です。
- 相槌や返事をする
- 作業をしていたら、手を止める
- 目線を合わせて話を聞く
受容と共感 保護者の話を受け入れる
人の話や意見にすぐ反発したくなる人は要注意。
「でも、だって…」が口癖な方もキケンです。
私もつい「それはさ…」なんて言いたくなりますが、まずはいっぺん全部受け止めましょう。
- そうだったんだね
- そう思った(感じた)んですね
- それは不安(心配)でしたね
謝罪の場合も一緒です。
- 不快な思いをさせて申し訳ございません。
- お父さん(お母さん)のおっしゃる通りだと思います
- そうですよね
受け止めてもらうことで気持ちが落ち着く人もいます。
気持ちを受け止めると同意するは違うので気をつけましょう。
「先生も同じ意見だって!」話が飛躍することがあります。
あくまで気持ちに寄り添い、その思いを受け止めることがポイントです。
積極性 保育士から話かける
保護者対応の第一歩として、積極的に自分から話しかけましょう。
- 休日はどうでしたか
- 涼しくなりましたね
- ○○ちゃんの髪型かわいい!お母さんがやったんですか?
- お父さんの帽子おしゃれですね
- お母さん、髪を縛ると印象変わりますね
- 今日こんなことがありましたよ
などなど。どんなことでもOK。
お願いしたいことや伝達事項、ケガの時だけに話しかけていませんか?
先生が話しかけてくる=何かあった
と思われるのはとても残念です。
始めは反応が薄い保護者も少しずつ返してくれるようになります。ぜひ積極的に話しかけてみてくださいね。
園長・主任・同僚への報連相
「これくらいはいっか…」
「相談していいのかな?」
と自己判断禁物。常に情報をオープンにしておきましょう。
絶対報連相すること
- ケガ
- 子どもの物品の紛失、破損
- その他保護者に謝罪したこと
- 園への保護者からの意見や指摘
- 自分だけでは判断できないこと など
「クラス内で起きたことだから…」と報告していないことで二次クレームにつながることもあります。
事例

By: Alex Guerrero
主任や園長に伝えなかったことで、保護者との信頼関係に影響するような事例をご紹介します。
年長組のよしこちゃんが顔をぶつけてしまいました。幸い傷にならず、赤みがでたもののアイスノンで冷やしたらひきました。
担任は保護者に謝罪し、様子をみてもらうよう伝えました。
翌日、登園時に園長先生と園庭であったよしこちゃんとお母さん。
園長先生は顔にあざができていることに驚き「そのあざどうしたの??」と尋ねます。
お母さんは「昨日、園で顔をぶつけたそうです。帰ったらあざになってきたのですが、園長先生はご存知なかったんですか?」と不満そうに出勤していきました。
その日の夕方にお母さんから「ケガをすることはあると思います。ですが、納得がいきません。園長先生が園内で起こったことをご存じないというのはどういうことですか?」とご指摘がありました。
この事例は、園内でのケガです。
本来であればケガをした日の謝罪で終了していました。
園長先生が園内で起きたことを知らなかった。
その事実にお母さんは不信感を抱きます。
当日に担任が報告。翌朝、園長先生がケガのことを知っていたら対応は変ります。
(例)
「よしこちゃん、昨日は痛かったよね。ごめんね。」
「お母さん、お顔にケガをさせてしまって申し訳ありませでした。」
担任は翌朝確認しようと考えていたでしょう。ですが、園長先生に園内で起きたことを報告しておらず、園長先生が知らなかった。それが園へ対する不信感につながった事例です。
「小さなケガだから…」の自己判断は園全体の信頼関係に影響することもあると肝に銘じておきましょう。
まとめ
何年たっても保護者対応に自信がもてなくなったり、自信がなくなることもあります。
逆に保護者の言葉に励まされることやうれしいと感じることも。
苦手・不安と思う方に少しでも保護者対応に前向きになってもらえたら嬉しく思います。
保護者と二人三脚で行う保育はきっと楽しいですよ。